日本の最新がん統計によると、がんの約6割は治るようになりました。
しかしながら、残り4割のがんは再発して、不幸にして命を落としてしまいます。
再発の多くは、がんの転移によるものです。
がんによる死亡を今以上に減らすためには、転移・再発がんをいかに克服していくかが課題といわれます。
局所にできたがんを取り除いても患者さんを常に不安にさせるがんの再発・転移。
そのメカニズムや治療目標について考えます。

がんの再発・転移とは? がんの大きな特徴は転移すること
がんは遺伝子の病気で、遺伝子が複数変化することで1つのがん細胞ができ、それが2つになり4つになりと指数関数的に増えていきます。
画像検査などで見つかる直径1cmほどの大きさになるまでは、がんの種類によっても異なりますが、約10年かかるとされています。
直径1cmのがんには数億個のがん細胞があるといわれています。
その段階でうまく外科的に切除できれば、治る可能性は高くなります。
しかし、実際は、がんが最初にできた場所(原発巣)を切除しても、原発巣が100万個ぐらいのがん細胞になったときには
すでにもう血液の中に出ていることもあるので、すでにがん細胞が全身を回っていることもあります。
原発巣近く(局所、領域)、あるいは他の臓器(遠隔)に残ったがん細胞から再びがんが生じることを「再発」と呼びます。
抗がん剤治療や放射線治療でいったん縮小したがんが再び大きくなったり、
別の場所にがんが出現したりするのもすべて「再発」です。
血液やリンパのがん、前立腺がんなどでは「再燃」という言葉が使われます。
がん細胞が最初に発生した場所から、血液やリンパの流れににって他の臓器や器官へ移動し、そこで増殖することを「転移」といいます。
前述したように、転移は局所・領域再発と並ぶ、重要な再発様式です。
転移したがん細胞によって形成されたがんは、原発巣に対して、転移巣とよばれます。
原発巣から転移したがん病変は転移した部位によって、たとえば、乳がんが肺に転移した場合は、肺がんではなく、「乳がんの胚転移」です。
いずれかの遠隔臓器に転移があれば、「転移性乳がん」とも呼ばれます。
乳がんが肺に転移してできたがんは、基本的にはもともとの乳がんと同じ性質をもっています。
この転移するということが実は大きな特徴です。
がんは悪性腫瘍とも呼ばれます。
腫瘍は複数の遺伝子の変化により生じ、周囲の状況に関係なくどんどん増殖していく病変のことで、
良性腫瘍と悪性腫瘍とに分かれます。
両者の共通した性質は、発生した場所(組織)とは無関係に細胞が増殖していくことです。
ただし、良性腫瘍は発生した場所にとどまり、その場で大きくなるだけです。
基本的には手術で取ってしまえば声明に直接危険を及ぼすことはありません。
一方、悪性腫瘍の場合は放置すると大きくなるだけでなく、
さらには近くのリンパ節、加えて遠く離れた臓器にも転移して、命に関わるような状況を招きます。
この転移するという性質が、ガンを重大な病気にしている最大の理由です。
転移はなぜ起こるか 転移の3つのパターン
人間の体を構成している無数の細胞は、通常はそれぞれの臓器や組織に固定されており、
赤血球や白血球などの血球以外は、その場所を離れて体内を勝手に移動することはありません。
なぜなら、細胞同士が互いにしっかり結びついているからです。
これは良性腫瘍でも同じで、組織内の細胞は自分の場所を離れれば死んでしまいます。
ところが、がん細胞は組織を離れても生き続けることができます。
そして、血液やリンパ液に混じって他の臓器や器官に転移し、そこで増殖を始めます。これが転移です。
転移のメカニズムは次のように考えられています。
がん細胞が上皮内(粘膜層)にできて増殖していくと基底膜(上皮細胞と間質細胞を境界している膜)を破って浸潤していきます。
基底膜の外にはリンパ管、血管があり、転移はそこにがん細胞が入って体内を回ることで起こります。
転移には3つのパターンがあり、
1つは血液の流れに乗って広がるもの(血行性転移)
2つめはリンパ管を流れるリンパ液に乗って広がるもの(リンパ行性転移)、
3つめは播種といって、がんのできた臓器からがん細胞が剥がれ落ち、腹腔や胸腔にばらまかれて広がるものです。
一番近い場所への転移は、原発巣の近くのリンパ節への転移で「領域転移」と呼ばれます。
転移の中ではこれが一番多いパターンです。
たとえば、乳がんならばわきの下のリンパ節、
胃がんならば胃を取り巻くリンパ節に転移することがよく見られます。
一方原発巣から遠い臓器に転移することを「遠隔転移」といいます。
遠隔転移は骨、肺、肝臓、脳などさまざまな場所に起こります。
遠隔転移の多くは、血行性転移です。
すべてのがん細胞が転移を引き起こすわけではなく、
血管やリンパ管に入り込んだがん細胞のうち、
長時間生き延びて別の場所で増殖できるようになるがん細胞は0.1%程度、
すなわち1000個に1個程度とされています。
最近は転移のメカニズムを細胞および分子レベルで解明する研究が進み、
遠隔転移を引き起こすメカニズムが明らかになってきました。
転移する過程には、細胞接着因子、蛋白分解酵素、増殖因子、血管新生因子、
ケモカイン(白血球やリンパ球など細胞を組織に遊走させるのに必要な物質)など
多くの分子が関与していることが判明しています。

がん細胞が遠隔転移を引き起こす際には、遺伝子の変化により、次のような現象を起こすと考えられています。
①周囲の組織との結びつきを失い、はがれやすい状態になる。
細胞と細胞は通常、しっかりとくっついています。
くっつける役割を果たしているのが、細胞接着因子と呼ばれるたんぱく質です。
がん細胞はこと細胞接着因子の発現を低下させるなどして細胞をはがれやすくします。
②運動能力を得て、組織内でふらふらと動き出す。
細胞が動くための装置が細胞の中にあります。
アクチンファイバーという繊維状の物質で、がん細胞はこれを壊したり、再構築したりして動きます。
③血管を成長させる物質(血管新生因子)を放出し、新しい毛細血管をつくりだして、がんの近くまで引き寄せる。
がんが成長し続けるためにはより多くの酸素や栄養が必要です。
そのために新しい血管をつくり(血管新生)、血液供給を確保します。
血管新生因子の中でも重要な働きをしているのがVEGF(血管内皮増殖因子)で、
がんがこの因子を放出することで新生血管ができます。
④血管の壁を溶かす物質を放出して血管内に入り込む。
がん細胞はMMP(マトリックス・メタロ・プロテアーゼ)などの
たんぱく質分解酵素を分泌して血管の壁を壊し、血管内に入り込みます。
⑤血流に乗って他の臓器や器官へと移動し、そこに付着して増殖を始める。
転移する臓器はなぜかほぼ決まっています。
がんの転移する性質というのは、基本的にはある程度の大きさになってから獲得すると考えられています。
多くのがんでは、直径1cm前後まではあまり転移しません。
なぜなら、がんが小さいうちは、組織中にある普通の血管から酸素や栄養を受け取っているからです。
ところが、がんが大きくなるにつれてそれだけでは酸素や栄養が足りなくなり、
がんの塊の中に新生血管を作り、そこを流れる血液から補給するようになります。
すると流れ込む血液が増え、がんの増殖がさらに進みます。
たくさんの新生血管ができることで、がんが遠くの臓器まで流れていきやすくもなります。
がんが転移するようになるのは、新生血管が多くできることも大きな原因の一つです。
転移しやすいがんと転移しやすい部位
米国国立がん研究所は「ガンは1つの病気ではなく、細胞が異常に増え続けるという性質を持つ100種類以上の病気の総称」と説明しています。
がんと一口にいっても性質はさまざまで、早いうちから転移や浸潤を始めるがんもあれば、ゆっくりと成長し、あまり転移しないガンもあります。
一般的には悪性度が高く、遺伝子の変化が多いとガンは転移しやすくなります。
転移しやすいがんには、乳がん骨肉腫、悪性黒色腫(メラノーマ)すい臓がんなどがあります。
周囲の組織に浸潤しやすいがんとしては、卵巣がん、スキスルと呼ばれる特殊な胃がんが知られています。
たとえば乳がんは、乳房の乳腺に発生しますが、腫瘍は小さくても早期からがん細胞がこぼれ落ちて周辺に転移しやすく、わきの下のリンパ節に転移します。
さらには骨や肺、肝臓、脳などに遠隔転移することもあります。一般的には転移や浸潤が早く始まるがんは、再発もしやすいとされます。
逆に、子宮頸ガンや甲状腺がんは遠隔転移を生じる頻度は低いとされています。 がんが転移しやすい部位もあります。
血液もリンパ液も全身を循環しているので、全身のどこに転移しても不思議はないはずですが、なぜか肝臓、肺、脳、骨などに限られています。
がんの種類によって転移しやすい部位があることも知られています。
たとえば、大腸がんや胃がんは肝臓や肺、腹膜、乳がんは骨、肺、肝臓、脳などです。
転移しやすい部位が決まっているのにはいくつか理由が考えられます。
1つは、血流の問題です。大腸がんや胃がん、肝臓がんといった消化器がんが転移しやすいのは肝臓です。
肝臓はいわば人体の化学工場です。胃や腸、すい臓などの消化管を通過した血液は、門脈という血管を通っていったん肝臓に向かいます。
胃や腸で生じたがん細胞も門脈の血液中に入り込むと、それは必ず肝臓に向かいます。
肝臓には毛細血管が網の目のように広がっているので、その行き止まりにがん細胞が引っかかって癒着し、そこで増殖が始まるとみられています。
肺も転移が多い部位です。胚は全身からの血液を受け取り、二酸化炭素を取り除いて酸素を供給します。
そのために肝臓と同様、肺の内部には毛細血管が網の目のように広がっており、やはり血管の行き止まりにがん細胞が癒着しやすい状態です。
毛細血管が多い脳も、転移しやすい部位の一つです。
脳内を通る血管は他の毛細血管より壁が厚く、血液脳関門もあって異物を通しにくい構造ですが、
がん細胞は血管壁のたんぱく質を溶かして血管壁を通り抜け、脳組織の中に入り込みます。
転移しやすい部位が決まっていることのもう一つの理由が、がんの種類と臓器の親和性です。
がんの種類によって転移しやすい臓器があることは古くから知られており、
がん細胞という”腫”が成長に適した”土壌”すなわち臓器に達したときのみ、転移が起こるという意味で「種と土壌の理論」と呼ばれてきました。
現在ではこの現象は、転移先の組織が分泌するケモカインと、がん細胞表面に発現するケモカインと
結合する受容体の関係で決まるのではないかなどと考えられています。

がんの悪性度とは
細胞が未成熟な状態からしだいにそれぞれの役割をもった成熟状態へと変わっていくことを「細胞の分化」といいます。
その過程は「未分化」から「低分化」へ、そして、「高分化」へと進みます。
一般に未分化の細胞ががん細胞に変わった場合には、高分化の細胞ががん化したものより「悪性度が高い」とされています。
1高分化がん
顕微鏡で見たときに姿形が明瞭ではっきりした細胞(分化のすすんだ細胞)ががん化したものをこう呼びます。
高分化のがん細胞は正常細胞に近い形をしており、一般に悪性度が低く、予後が良いとされています。
2中分化がん
細胞の分化度、悪性度とも高分化がんと低分化がんの中間の性質をもつものです。
3低分化がん
もとの細胞の分化が低く、より速く増殖・転移するため悪性度が高いとされています。予後はよくありません。
4未分化がん
まったく分化が進んでおらず未成熟で、もとの細胞の性質を確認できないがんをこう呼びます。
低分化がんよりもさらに分化度が低く、増殖・転移もより速いため、もっとも悪性度の高いがんです。一般的に予後はきわめて悪いとされています。
転移または再発しやすいがん
他の組織や臓器に転移・浸潤しやすいがん
がんの種類 乳がん
転移・浸潤先の部位 肺、肝臓、脳、骨
がんの種類 骨肉腫
転移・浸潤先の部位 胚、肝臓、脳、骨
がんの種類 卵巣がん
転移・浸潤先の部位 子宮、大網、大腸、腹膜
がんの種類 すい臓がん
転移・浸潤先の部位 十二指腸、胆管、肝臓、血管、神経、腹膜
がんの種類 メラノーマ
転移・浸潤先の部位 リンパ節
がんの種類 スキルス胃がん
転移・浸潤先の部位 腹膜
再発しやすいがん
肝臓がん、すい臓がん、食道がん、膀胱がん(がんの組織のみを切除したとき)、直腸がん、(手術で肛門の機能を残したとき)
再発がんは悪性度が高い再発・転移への対応も
がんは治療後2~3年以内に再発することが多く、多くのがんでは遅くとも5年以内には再発するといわれています。
したがって、治療から5年までに再発するかどうかが1つの目安になります。5年経っても再発しなければ、一般に完治したとみなされます。
ただし、乳がんや腎臓がん、甲状腺がんのように10年以上経ってから再発する例もあり、油断はできません。
再発したがんは、その成り立ちと部位によって、局所再発(最初のがん発生場所の近くのリンパ節または組織で成長する)、
遠隔再発(最初のがんの発生場所から離れている器官または組織に転移する)に分かれます。
局所転移や領域転移の場合は外科的に転移巣とその近隣のリンパ節を切除したり、放射線を照射したりすることである程度コントロールすることができますが、
遠隔再発したものは今の医学では治すことはなかなか難しいのが現状です。 遠隔転移に限らず、再発したがんの治療は一般的に困難です。
もともとがん細胞は均一ではなく、細胞に多様性が見られます。再発したがんは悪性度の高い細胞の比率が高まる、あるいは悪性度がさらに悪化する傾向があります。
がん細胞は遺伝子の変化によって徐々に悪性化します。遺伝子の変化が多いものは転移しやすいといわれます。
再発を引き起こしたがんは浸潤や転移に必要な能力を身につけているともいえます。 治療の面でも、再発がんは制約が多くなります。
例外的には、大腸がんや肉腫などは転移巣を再度手術して治ることもありますが、
多くの場合、転移巣を1つ取ってもまたすぐに出てくるモグラたたき状態になってしまい、手術してもあまり意味がないといわれます。
また、抗がん剤投与を受けている場合、最初は薬剤感受性が高いがん細胞が死滅して効果が見られても、徐々に抗がん剤の効果が消失します。
しかしその後ある時期に薬剤に対する抵抗性(薬剤耐性)を有するがん細胞が増えて、進行します(Progression Disease:PD)。
放射線治療でも、一度照射したところに再照射すると臓器が致命的な損傷を受けることがあり、再照射できないこともよくあります。
近年は、再発予防のために初回の手術後などに抗がん剤を投与したり、放射線を照射したりする術後補助療法が行われています。
がんが1cmの大きさになったときはどこかにがん細胞が残っている可能性があります。
治癒率を高めるためには、そうした目に見えない体に残っている1万~100万個程度のがん細胞(微小転移)を抗がん剤などで叩くと、がん細胞をゼロに近くすることができます。
また人により異なりますが、人間の免疫力もけっこうあって、10万個以下のがん細胞なら人間の免疫細胞でかなり抑制できるといわれています。
米国では術後に抗がん剤やホルモン剤の治療をしっかりやり、根治率を上げることに熱心に取り組んでいます。
しかし、ひとたび全身再発したときは、多くの場合、結果として助けることはできないので、
むしろ残された人生は高いQOLに重点をおいて、治療をやっていこうという明確な考え方があります。
日本はその辺がまだ曖昧で、術後補助療法や緩和医療の遅れにつながっています。

再発・転移がんの治療目標
全身療法で延命を目指す
がんの治療は、手術、薬物治療(抗がん剤、ホルモン剤、分子標的薬など)、放射線治療が三本柱です。
そのうち、手術と放射線治療は局所に対する治療です。一方、薬物治療は全身のがん細胞に効きます。
がんが再発した場合、全身に作用する抗がん剤やホルモン剤を投与することで転移巣に効かせ、結果として延命を目指すことが治療目標になります。
基本的に、転移巣にも原発巣と同じ治療をします。たとえば乳がんの肺転移なら、肺がんではなく、乳がんの治療を踏襲して行います。
ただし、遺伝子が変化したがん細胞が転移してくるので、原発巣とは性質が多少違ってくる可能性があります。
同じ薬が効くかどうかは投与してみないとわからないところがあります。
乳がんの場合、原発巣ではホルモン受容体が陽性だったのに、転移巣では陰性になっていることはよく経験します。
ホルモン受容体陽性の場合には、まずはホルモン剤を使ってみて、効かなかったら異なるホルモン剤を順次投与します。
ホルモン剤が尽きた場合には、抗がん剤を投与することになります。
再発がんに対しても今は効果のある分子標的薬がいろいろ開発され、上市されています。
たとえば大腸がんは、抗がん剤のフルオロウラシルが薬物治療の中心だった時代は、再発したら、どのくらいいきられるか
という延命効果を示す指標である生存期間中央値は6~12カ月とされていました。
ところが、殺細胞効果の高いオキサリプラチンやイリノテカンを加えることにより、生存期間中間値は大幅に延長しました。
加えて、分子標的薬のベバシズマブが2007年4月に承認されてから、セツキシマブ、パニツムマブが相次いで承認され、
それらの分子標的薬を組み合わせた多剤併用療法によって、生存期間中央値は現在36カ月以上に延長しています。
ベバシズマブはVEGFを標的にした血管新生阻害薬です。
がんが転移するようになる原因の一つは新生血管ができることですから、それを阻害する働きがあります。
セツキシマブやパニツムマブは肺がんに使われる分子標的薬のゲフィチニブを同様、
がん細胞の分裂に関与するEGFR(上皮細胞増殖因子受容体)を阻害することで抗がん作用を示します。
がん細胞にEGFRが発現している人に有効です。 ここでも問題になるのは薬剤耐性です。
最初の治療でたとえ99%のがんがなくなったとしても、残り1%のより悪性度の高いがん細胞がまた増殖してくると
最初に使った薬は効かず、また別の薬を使わないといけません。
再発がんに対する薬物治療は、たとえば大腸がんの場合、一次治療から5次治療まで選択肢があります。
まずは一次治療から開始し効果が低下したときは2次、3次と順次治療を続けていきます。
がんの種類や患者さんの体調にもよりますが、三次治療のころには患者さんも体力が低下するなどして、
薬を減量したり、化学療法を終了して、緩和医療だけにしたりすることが増えてきます。
再発・転移がんの克服に向けてがん幹細胞の研究も
再発・転移がん治療の主力として期待されるのはやはり薬物治療です。
抗がん剤のほとんどは殺細胞効果がある細胞毒と呼ばれるタイプのもので、
細胞の分裂に関わるさまざまな相に作用し、がん細胞を破壊します。
こうしたタイプの抗がん剤の開発はもう限界にきているといわれます。
地球上に存在する材料となる物質はほぼ出尽くしたと考えられているからです。
現在、盛んに開発されているのが分子標的薬です。
近年の研究で、がん細胞の増殖や転移に関するバイオマーカーがわかってきました。
その代表格が前述したベバシズマブなどの血管新生阻害薬です。
転移のメカニズムがいろいろとわかってきたことで、血管新生阻害薬以外にも、
転移を抑制する新しい治療薬の研究が世界中で行われており、
今後も新しい分子標的薬が開発されると考えられています。
ただ、分子標的薬にも問題はあります
。分子標的薬は殺細胞効果を有する抗がん剤と比較すると、
がんのバイオマーカーに特異的に作用するので副作用が少ないといわれていますが、
かなり強い皮膚症状がでることがあります。
ゲフィチニブやセツキシマブ、パニツムマブはEGFRを標的にした薬ですが、
このEGFRは正常な皮膚の上皮細胞にもたくさん存在しており、
そこにも作用して副作用として出てしまうのです。
開発費がかかるので高価なのも難点です。
分子標的薬でもっとも成功したのは乳がんのトラスツズマブですが、
それ以外は効果が限定され、分子標的薬単剤ではなかなか効きません。
そこで殺細胞作用がある抗がん剤と併用して
延命効果を得られるような組み合わせがいろいろと工夫されています。
最近、がん細胞の中には抗がん剤や放射線治療に抵抗性を有するがん細胞のオリジナルで、
未分化な細胞があることが報告され「がん幹細胞」と呼ばれています。
それを叩かない限り、がんの転移・再発は治らないのではないかともいわれ、
がん幹細胞に対する研究が注目されています。
がん幹細胞がどのくらいの頻度で見つかるか、
それに対してどういう薬が有効なのかなど、研究はまだ始まったばかりです。

手術による治癒が難しい進行・再発大腸がんに対する化学療法
強力な治療が適応となる場合の薬物療法
用法 A
一次治療 【①または②】
①FOLFOX ±ベバシズマブ
②カベシタビン +オキサリプラチン±ベバシズマブ
二次治療 【①~③のいずれか】
①FOLFIRI±ベバシズマブ
②イリノテカン+テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合(S-1)
③イリノテカン
三次治療 【①~④いずれか】
①イリノテカン+セツキシマブ
②イリノテカン+パニツムマブ
③セツキシマブ
④パニツムマブ
四次治療 【①または②】
①レゴラフェニブ
②対症療法
用法 B
一次治療 【①または②】
①FOLFOX ±ベバシズマブ
②カベシタビン +オキサリプラチン±ベバシズマブ
二次治療 【①~④いずれか】
①FOLFIRI±セツキシマブ
②FOLFIRI±バニツムマブ
③イリノテカン±セツキシマブ
④イリノテカン±バニツムマブ
三次治療 【①または②】
①レゴラフェニブ
②対症療法
用法 C
一次治療 FOLFOX ±ベバシズマブ
二次治療 【①または②】
①FOLFOX ±ベバシズマブ
②カベシタビン +オキサリプラチン±ベバシズマブ
三次治療 【RAS野生型の場合①~④のいずれか】
①イリノテカン+セツキシマブ
②イリノテカン+パニツムマブ
③セツキシマブ
④パニツムマブ
四次治療 【①または②】
①レゴラフェニブ
②対症療法
用法 D
一次治療 【RAS野生型の場合①または②】
①イリノテカン+セツキシマブ
②イリノテカン+パニツムマブ
二次治療 【①~③のいずれか】
①FOLFIRI±ベバシズマブ
②イリノテカン+テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合(S-1)
③イリノテカン
三次治療 【①または②】
①レゴラフェニブ
②対症療法
用法 E
一次治療 【RAS野生型の場合①または②】
①イリノテカン+セツキシマブ
②イリノテカン+パニツムマブ
二次治療 【①または②】
①FOLFOX ±ベバシズマブ
②カベシタビン +オキサリプラチン±ベバシズマブ
三次治療 【①または②】
①レゴラフェニブ
②対症療法
用法 F
一次治療 FOLFOXRI
二次治療 【RAS野生型の場合①~④のいずれか】
①イリノテカン+セツキシマブ
②イリノテカン+パニツムマブ
③セツキシマブ
④パニツムマブ
三次治療 【①または②】
①レゴラフェニブ
②対症療法
用法 G
一次治療 【①~③のいずれか】
①フルオロウラシル+レボホリナート±ベバシズマブ
②カペシタビン±ベバシズマブ
③デガフール・ウラシル配合(UFT)+ホリナート
二次治療 A~F用法の一次治療からいずれかを選択
三次治療 A~F用法の二次治療からいずれかを選択
四次治療 A~F用法の三次治療からいずれかを選択
五次治療 【①または②】
①レゴラフェニブ
②対症療法
●FOLFOX=フルオロウラシル+レボホリナート+オキサリプラチン
●FOLFIRI=フルオロウラシル+レボホリナート+イリノテカン
●FOLFOXIRI=フルオロウラシル+レボホリナート+イリノテカン+オキサリプラチン

強力な治療が適応とならない場合の薬物療法
用法 A
一次治療 【①~③のいずれか】
①フルオロウラシル+レボホリナート±ベバシズマブ
②カペシタビン±ベバシズマブ
③デガフール・ウラシル配合(UFT)+ホリナート
二次治療 対症療法
用法 B
一次治療 【①~③のいずれか】
①フルオロウラシル+レボホリナート±ベバシズマブ
②カペシタビン±ベバシズマブ
③デガフール・ウラシル配合(UFT)+ホリナート
二次治療 可能となる最適な治療を選択
三次治療 対症療法
再発・転移がんの患者さんの多くは、残念ながら完全に治すことは難しいので、ゴールは延命と緩和。
延命という希望を捨てない中で、そうやって副作用を減らして、QOLを上げるかを考慮することが大切。
抗がん剤には吐き気や便秘などの消化器症状多いので、できるだけ副作用を減らし、快適に過ごせるように配慮することが大切。
緩和で麻薬系の薬剤が処方されている場合は、それが原因で便秘になることがある。
最近はTS-1やゼローダなど経口の抗がん剤や経口の分子標的薬を投与する機会が増えていて、遭遇する機会が多い。
経口の抗がん剤にもそれなりの副作用がある。
新しい抗がん剤の、特に副作用に関する知識を得て、患者さんに的確に情報を伝えていきたい。
制吐剤も中枢系の吐き気と末梢系の吐き気では使用する薬が違うので、症状を聞いた上でアドバイスする。

「患者様の症状、体質、病態に、よく適合した、より効果的な、抗がん活性を持つ漢方薬
(生薬、薬草、薬用動植物、健康食品)を、調合致します。」
「まずは、お電話ください。 0283-22-1574(大山漢方で、イゴ(不安)ナシ)」
お問い合わせは、
漢方を現代病に活かす!漢方専門 大山漢方堂薬局
0283-22-1574(大山漢方で、イゴ・不安・ナシ)
まで、お問い合わせください。
大山漢方堂薬局
漢方健康相談コーナーへ、クリック!

佐野厄除け大師通りの漢方専門、大山漢方堂薬局 Web-Page へ、Go!!!







医薬品は使用上の注意をお読みいただき、正しくお使いください。
お買い求めの際には、漢方を現代病に活かす 漢方専門 大山漢方薬局に、お気軽にご相談ください。

「インターネットで見た!」
とお話ください。
(注意)
漢方専門 大山漢方堂薬局の 厳選、漢方薬、健康食品のご注文は、大山漢方薬局に、直接、お電話、FAX、E-mail にてご用命ください。
お電話:0283-22-1574、FAX:0283-22-1607、E-mail:ohyama@poem.ocn.ne.jp
お待ち致しております。
「大山漢方堂 漢方医学と漢方健康相談」
 大山漢方堂薬局の得意とする病気、大山漢方堂薬局に漢方相談のあるご病気一覧、
大山漢方堂薬局の得意とする病気、大山漢方堂薬局に漢方相談のあるご病気一覧、大山漢方堂薬局 漢方健康相談窓口、医学博士大山博行先生、医学博士小松靖弘先生のご紹介
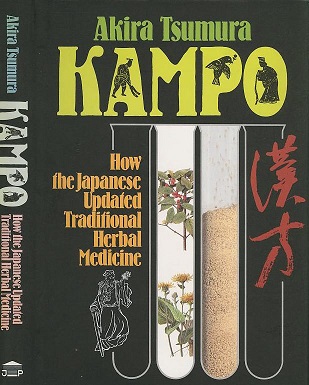 " THE KAMPO " 漢方
" THE KAMPO " 漢方漢方薬, How the Japanese Updated Traditional Herbal Medicine
<漢方薬のご服用をお考えの皆様へのお願い!>
*漢方薬のご服用に関しましては、
「使用上の注意」をよく読み、「用法・用量」をよく守り、適切にご服用ください。
また、今回、始めて、漢方薬のご服用を希望されるお客様は、
下記、問診表に必要事項を記入して送信するか、
 漢方相談お申し込みフォーム
漢方相談お申し込みフォームお電話にて、直接、大山漢方薬局に、ご相談ください。
症状・体質を詳しくお伺いした上で、適切な漢方薬をアドバイスさせて頂きます。
(大山漢方薬局 / 無料漢方相談電話 0283-22-1574 / 9:00~19:00)
<注意>
大山漢方薬局、デジタル店舗で、お取り扱いの漢方薬は、すべて「一般用医薬品」です。
以上、よろしくお願い致します。
 E-mail to Dr. Ohyama Kampo Pharmacy.
E-mail to Dr. Ohyama Kampo Pharmacy.大山漢方堂薬局 〒327-0026 栃木県佐野市金屋仲長町2432
TEL&FAX : 0283-22-1574 E-mail : ohyama@poem.ocn.ne.jp
(Ⅰ)がん免疫療法のしくみ
①手術、②抗がん剤、③放射線、に次ぐ第4の治療法として期待されるのが、④がん免疫療法である。
いくつかの免疫チェックポイント阻害薬の効果が認められ承認された=がん治療におけるがん免疫療法の位置づけが変わった。
「免疫チェックポイント阻害薬」
がん免疫療法とは、ヒトに備わっている免疫防御機構を使って、がんを治そうという治療法である。
がん免疫療法の歴史
非特異的免疫賦活剤がんワクチン、サイトカイン療法(サイトカインを注射して免疫細胞に活性化する)、
モノクローナル抗体療法(ヒトのがん細胞に対する抗体をマウスを用いて作る)
非特異的免疫賦活剤やサイトカイン療法は、体全体の免疫を底上げして、がんと闘う。
がんワクチンは、臨床試験ではフェーズⅠ(副作用などの安全性について確認する第Ⅰ相試験)、
フェーズⅡ(少数の患者さんで、有効で安全な投与量・投与方法などを検討する第Ⅱ相試験)までは比較的よい結果が出る。
フェーズⅢ(多数の患者さんで、有効性を確認する第Ⅲ相試験)で、人数を増やすと有効性の有意差がつかない=標準治療にならない。
モノクローナル抗体療法は、患者さん自身が作る抗体ではないが、Her2やCD20やVEGFに対する抗体が標準のがん治療となる。
「免疫チェックポイント阻害薬」
1990年代に入り、免疫細胞が、がん細胞を攻撃するメカニズムが次々と明らかにされた=がん細胞に特異的ながん免疫療法の研究が進歩。
免疫チェックポイント阻害薬は、2000年代に入って臨床試験が始まり、フェーズⅢでも明確に効くことが示された。
最初の臨床試験は抗がん剤が効かない悪性黒色腫(メラノーマ)の進行がんに対して行われ、治療効果を表す奏効率は約30%。
しかも、最初の悪性黒色腫に対する臨床試験では、持続的な治療効果も報告された。
進行した悪性黒色腫であっても約2割に長期生存がみられた。
米国の臨床試験では、免疫チェックポイント阻害薬の1つであるCTLA-4阻害拮抗体薬(イピリムマブ)では、
10年生存率は薬20%、抗PD-1抗体薬(ニボルマブ)の5年生存率は34%で、3人に1人は5年以上生存できるという奏効率が得られた。
がん免疫療法の長所
①他の薬が効かなくなった、がん患者さんも一定の割合(10~30%)で明確な治療効果を示す。
②しかも人によっては比較的持続的な効果が得られる。
従来のがん免疫療法における腫瘍縮小効果はないが、標準治療後の再発予防や延命は可能。
本当に効くがん免疫療法は進行がんに対しても有効である。
臨床の場で、がん免疫療法の位置づけが一変した。
今多くの製薬メーカーが、免疫療法の開発に力を入れ始めた。
現時点では、多くのがん患者さんでの奏効率は10~30%で=実は効かない症例のほうが多い。
自然免疫と獲得免疫とは?
免疫とは、病気を引き起こす細菌やウイルスなどの異物から体を守る仕組みの総称。
ヒトの免疫は、自然免疫系と獲得免疫系に大別される。
まず自然免疫系が働き、その後に獲得免疫系が働く。
①獲得免疫
獲得免疫で、重要なのは、リンパ球のT細胞とB細胞である。
抗原特異性と多様性、免疫記憶と呼ばれるメモリー機能を持つことが特徴。
抗原特異的なリンパ球が爆発的に増えて強力な効果を生みだす。
がん免疫療法のしくみに深く関わるのがT細胞
=T細胞はその細胞表面にT細胞受容体(T cell Receptor: TCR)を持っており、
このTCRを介して細胞やウイルスなどの異物が持つ目印(抗原)を認識することで活性化する。
この目印に特異的な反応を 「抗原特異的」 と呼ぶ。
私たちの体内に存在するT細胞はそれぞれ異なるTCRを持ち、その数は10の十数乗にも及ぶ。
これが、「多様性」で、ありとあらゆる抗原に対応できる。
「免疫記憶」は、予防接種を考えるとわかりやすい。
子供に、麻疹ワクチンを接種しておけば、大人になっても麻疹にかからない。
これは、麻疹ワクチンを目印として記憶したT細胞(メモリーT細胞)が、長期間にわたって体の中に存在し続けるから。
ある感染症に一度かかると二度とかからないのは免疫記憶があるから。
B細胞は、その細胞表面に抗原特異的に反応するB細胞受容体を持ち、
それが細胞から、はずれて抗体となり、様々な異物に反応する。
例えばインフルエンザの抗体はウイルスを除く。
②自然免疫
自然免疫系は、好中球、マクロファージ、樹状細胞などの貧食細胞やNK細胞。
細菌やウイルスなどの異物が入ってくると、まずは自然免疫系が働き、好中球などの白血球が食べて異物を排除する。
食べて全部排除できればよいが、それだけでは抑えられないので、その後に獲得免疫系が働く。
その際、自然免疫と獲得免疫の橋渡し役になるのが樹状細胞である。
樹状細胞は体のあちこちにあり、がんであれば壊れたがん細胞の破片を取り込み、
撃するべき細胞の目印(抗原)をT細胞に提示するという役目を担う。
がんと免疫の関係
免疫監視機構を逃れてがん化!
この免疫防御機構を単にどう効かせるかが問題です。細菌やウイルスなど外から入ってきた異物に対しては強い免疫反応が起こるので排除できますが、がん細胞はもともと自分の細胞が遺伝子異常(人間の体の設計図であるDNAに傷がついたり〔塩基配列の変異〕や遺伝子の発現異常が起こる)を起こして増殖したものです。通常、正常な細胞は互いにくっつくと制御し合って増殖が止まります(接触阻害)が、DNA異常でその調節がきかなくなると、その細胞は無限に増殖するがん細胞に姿を変えていきます。体内ではがん細胞の元になる遺伝子の異常をもつ細胞が生み出されています。
遺伝子異常が起こる原因としては、紫外線、放射線、タバコ、発がん物質などの外因性要因と、細胞分裂時に偶然起こるDNAのエラーや活性酸素によるダメージなどの内因性要因があります。一般的には、がんは喫煙や紫外線など外因性要因によって起こると思われがちですが、DNAのコピーエラーなどの内因性要因によるものが多いとの報告もあります。
さて、私たちの体内では、遺伝子異常をもつ細胞が生まれていますが、それがそのままがんになるわけではありません。遺伝子修復などの様々な体の防御機構がありますが、その一つとして免疫監視機構と呼ばれるしくみが、がんの発生を防いでいます。樹状細胞はがん細胞の一部を貧食すると、がん細胞内のたんぱく質をアミノ酸薬10個からなる短いペプチド(抗原)に分解し、それをHLA(ヒト白血球抗原)と呼ばれる細胞表面分子を介して、細胞外に提示させます。T細胞上のTCRは抗原べプチドを細胞表面で提示させます。T細胞上のTCRは抗原ペプチドを細胞表面で提示するHLAとの複合体を認識し、活性化します。がん細胞の場合、ペプチドはがん抗原と呼ばれ、それに反応するT細胞ががんを攻撃するキラー細胞となります。
一方、がん細胞も生き残りをかけて巧妙な罠を仕掛けてきます。T細胞に認識されるたんぱく質を出さずに獲得免疫を逃れたり、免疫にブレーキをかけるたんぱく質を作って、免疫の働きを抑えたりします。こうしてがん細胞が増殖していきます。さらに、がんが増殖するにつれて、がんの組織内でがん細胞自体も変化して、免疫による排除や治療が難しくなっていきます。
通常、体は異物が入ると反応して免疫が活性化されますが、活性化されたままだと体が壊れてしまうので、普通の状態に戻るための免疫抑制機構(ブレーキ)があります。また、免疫が自分の体を壊さないように抑えるシステム(自己免疫寛容)も備えています。これがうまく働かなくなって起こるのが自己免疫疾患です。がん細胞は、本来有害な免疫反応を抑えるためのブレーキである免疫抑制機構を働かせて、免疫防御機構から逃れていることがわかってきました。がん細胞は、体に備わっている免疫を抑える機構を「悪用している」のです。実際、臨床で見られるがん細胞は免疫抵抗性や抑制性を獲得していることが観察されています。
免疫チェックポイント阻害薬
その仕組みと効果は?
がん免疫療法は大きく分けると2種類あります。①がんに対する免疫を強める「アクセルを踏む」方法と、②がん細胞がかけた免疫の「ブレーキを外す」方法です。前者にはがんワクチン療法、サイトカイン療法、培養T細胞を用いた養子免疫細胞療法(後述)などがありますが、ごく一部のサイトカイン療法や非特異的免疫賦活剤以外には、有効性や安全性が確立されて標準治療になっている方法はありません。明確ながんに対する治療効果が明らかになっている免疫チェックポイント阻害薬は後者です。
免疫のブレーキ役の1つが、免疫チェックポイント機構です。免疫チェックポイント機構に関わる分子には、T細胞上に発現するPD-1、CTLA-4などがあります。がんは、免疫から逃れられるような特殊な環境(がん微小環境と呼ばれる)を形成しており、その微小環境を構成するがん細胞やマクロファージなど細胞表面には、PD-L1という膜タンパクが発現することがあります。PD-1とPD-L1は鍵穴と鍵のような関係にあり、結合するとT細胞の機能にブレーキがかかってしまいます。CTLA-4とペアになるのは抗原提示細胞上のCD80/86という分子です。
免疫チェックポイント阻害薬として使われているのは、免疫チェックポイント分子に結合してブレーキをかける機能を阻害するモノクローナル抗体で、抗PD-1/PD-L1抗体、抗CTLA-4抗体があります。これらの抗体が免疫チェックポイント分子同士の結合を阻害することで、免疫に対するブレーキを解除し、T細胞ががん細胞を攻撃できるようにします。
PD-1/PD-L1阻害薬治療では、最初は悪性黒色腫のみだった適応は、肺がん、腎細胞がん、ホジキンリンパ腫、頭頸部がんへと広がり、さらに胃がんなどさまざまながん種で臨床試験が進んでおり、一定の治療効果が示されつつあります。
最近は、免疫チェックポイント阻害薬がどんなに効くかも徐々にわかってきました。DNAの異常は大きく分けて、①遺伝子に傷がつくパターン、まる2エピジェネティクスといって、環境などによってDNAの塩基配列の変化を伴わずに遺伝子の発現が変わっていくパターンの2つがあります。このなかで、遺伝子に傷がついてアミノ酸が変わったためにがん細胞にだけ発現するペプチド抗原が、がんを攻撃するT細胞の標的として重要であることがわかり、免疫チェックポイント阻害薬の効果にも関係します。
遺伝子に傷がつく場合、がんの増殖、浸潤、転移に関わる「ドライバー変異」と、がん細胞の蔵書kなどとは直接関係のない「パッセンジャー変異」に分けられます。例えば、分子標的薬はがんだけに起こっている遺伝子異常に対して、それをピンポイントで叩くように作られます。分子標的薬の開発者は、ドライバー異変のような、がんの増殖に関与する遺伝子を見つけて、そのタンパクに対する阻害薬を開発します。一方、パッセンジャー変異は、傷はたくさん付いていても、その傷自体は竿房の異常増殖にあまり関係がなく、昔はゴミのような、何もしていない変異と考えられていました。ところが、免疫チェックポイント阻害薬によってパッセンジャー変異が改めて注目を集めることになりました。免疫チェックポイント阻害薬を投与した後、がんに特異的なT細胞が増え、それががん細胞を排除してくれます。そのターゲットはいろいろありますが、なかでも重要なのが、パッセンジャー変異が起こったところのタンパク質であることがわかってきました。最近はこれを「ネオ抗原」と呼んでいます。今まではなかったが、DNAがきずついたせいで新しくがん細胞特有のタンパクが作られ、それが免疫チェックポイント阻害薬を投与したときに標的になって、T細胞が活性化されます。逆に言うと、ネオ抗原を持っていない人には免疫チェックポイント阻害薬が効きにくい可能性があります。前述したように奏効率は悪性黒色腫で、10~30%、他の多くのがんではたかだか10~20%です。効かない人のほうが多いのです。
免疫チェックポイント阻害薬が効かない人への対応が課題
このように免疫チェックポイント阻害薬が効く人の理由が一部わかってきました。一つは遺伝子にたくさん傷がついて、T細胞のターゲットとなるネオ抗原が多いタイプが効きやすいことです。同じがん種でも、患者さんによってDNA変異の数は個人差があります。変異が10個しかない人もいれば、3000個ある人もいるなど千差万別なのです。たとえば肺腺がんの場合、喫煙者はDNA変異が多く、こういう人はT細胞のターゲットもたくさん持っているので、免疫チェックポイント阻害薬が効きやすい傾向にあります。
逆に効きにくいのはDNA変異が少ないがんです。肺がんでは、非喫煙者の肺腺がんで、EGFR遺伝子やALK遺伝子変異などのドライバー変異で起こったがんは、喫煙や炎症などによって長い期間をかけて多くのDNA変異をもつ肺扁平上皮がんと異なり、DNA変異が少ない場合が多く、免疫チェックポイント阻害薬が効きにくい場合が多いです。逆に、このようながんでは、ドライバー変異をターゲットとしたゲフィチニブなどの分子標的薬が効きます。
その一方で、遺伝子に傷がたくさんあっても必ずしも効かないこともわかっています。傷、すなわちT細胞のターゲットが存在しても、他の因子のためにがんを攻撃するT細胞ががんの中に入ってこれない状態などの問題があり免疫チェックポイント阻害薬が効かない場合も多いことがわかっています。その問題の仕組みはさまざまで、これをうまく除く方法があれば、それを併用することによって、免疫チェックポイント阻害薬を効くように変えることができるかもしれません。肺がんの薬80%、悪性黒色腫の約60%は、がん細胞に対するT細胞が十分に誘導されていないので、この場合、免疫チェックポイント阻害薬に他の治療法をプラスする(複合がん免疫療法)ことで、免疫チェックポイント阻害薬単独では効かない人を効くようにしようという研究が世界中で行われています。すでに米国を中心に数百の臨床試験が進行中で、一部では併用による治療効果の増強が認められています。
単剤免疫療法kら複合的免疫療法へT細胞利用免疫療法も期待
抗がん剤治療では多剤併用療法が一般的ですが、免疫療法も複合免疫療法によりさらに高い効果が得られることが期待されています。現在、臨床試験で明らかになっているのが抗PD-1抗体と抗CTLA-4抗体の併用です。悪性黒色腫の場合、抗PD-1抗体単独で治療すると奏効率は3割程度でしたが、抗CTLA-4抗体を併用すると奏効率は6割程度になったと報告されています。これは、免疫に対してブレーキを解除する薬同士の組み合わせです。
免疫療法同市だけでなく、従来の標準がん治療である、化学療法、分子標的薬、放射線治療との併用も多数試みられています。これらは、投与の量や方法によって、単にがん細胞を障害するだけでなく、免疫反応を活性化させる作用のあるものも報告されています。現在、さまざまな複合免疫療法で、治療効果が上がる可能性が報告されており、今後、さらなる評価により、承認されていくと考えられます。
一方、免疫チェックポイント阻害薬が効かない症例や苦手とするがんでは、がんを特異的に認識するT細胞を体外で培養して投与する養子免疫細胞療法も進められています。悪性黒色腫と子宮頸がんでは、腫瘍浸潤T細胞を培養したTIL療法の効果が示されていますが、他のがんではうまく行かず、がん抗原を認識する受容体を人工的に作成して、その遺伝子を導入したT細胞(TCRT,CART)を用いた養子免疫療法の開発も進められています。
がん免疫療法は副作用が問題
今後の課題は?
がん免疫療法で問題になるのは副作用です。免疫チェックポイント阻害薬は免疫のブレーキ機構を解除する治療法なので、がんに対する免疫力は上がりますが、場合によっては自己免疫疾患のような副作用が起こります。そのため、抗がん剤治療とはまったく違った副作用が多く観察され、あらゆる臓器に様々な自己免疫反応による症状が生じる可能性があります。間質性肺炎、心筋炎など重篤な副作用もあり、大腸炎、重症筋無力症、甲状腺機能異常、Ⅰ型糖尿病などさまざまな自己免疫反応が起こり、臓器を障害します。今までの抗がん剤と全く違う副作用が予測不可能で起こるので、早期発見、抗体の中断、免疫抑制剤の使用など早期の対応が必要です。そこで免疫チェックポイント阻害薬を使うときは、患者さんも含めて医療従事者が免疫のしくみの概略を勉強し、なぜこのような副作用が起こるのかを理解したうえで使用し、対応することが大切です。
現在、免疫チェックポイント阻害薬が効く可能性が高いのかどうかなど、がん患者さんの免疫状態がどのような状態にあるのかを評価できるようなバイオマーカーの研究が世界的に進められています。がんは人によって免疫の状態が違います。免疫チェックポイント阻害薬が効きにくい人に投与しても無駄になり、効く人にはしっかり使えばよいので、そのためにも効く人と効かない人を見分けるバイオマーカーの開発が重要課題となっています。またいつまで投与すべきかを判定する指標を見つけることも課題になっています。
がんの薬物ちりょうではすでに、その人に合った薬を使う「個別化医療」が進んでいますが、がん免疫療法も同じで個別化医療の実現が重要と考えられます。同じがん種であっても患者さんごとに生じている遺伝子変異が異なります。がん細胞の遺伝子変異は免疫療法の効果にも関係します。患者さんごとにがん免疫状態を評価して、より適切な免疫療法を行えるようになることが今後の目標です。
免疫チェックポイント阻害薬の副作用として予測される症状
頭痛(下垂体炎、下垂体機能低下症)
めめい(投与時の急性反応)
目の痛み、充血、視力低下、飛蚊症、光を過度にまぶしく感じる、
涙が出る(ぶどう膜炎などの眼障害)
視野が欠ける(下垂体)
甲状腺の腫れ(甲状腺機能亢進症)
咳、息切れ、呼吸困難(間質性肺炎)
動悸(甲状腺機能亢進症)
食欲減退、吐き気・嘔吐
腹痛、下痢、排便回数の増加、血便(大腸炎・消化管穿孔)
手のふるえ(甲状腺機能亢進症)
倦怠感、悪寒、発熱
(間質性肺炎、肝障害、下垂体炎、下垂体機能低下症、甲状腺機能低下症、副腎機能不全、1型糖尿病、投与時の急性反応)
汗をかく、体重減少、不眠(甲状腺機能亢進症)
かゆみ(皮膚障害、肝障害)
皮疹、白斑、紅斑(皮膚障害)
むくみ、(甲状腺機能低下症、腎障害)
リンパ球や白血球の減少
片側あるいは両側の脱力感、感覚異常、知覚障害、筋力の低下(重症筋無力症、末梢神経障害)